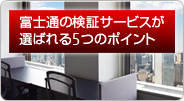所内共通クラウドを支えるネットワークを「Brocade VDX series」で刷新
回線の10G化・冗長化、論理スイッチで運用コスト半減を目指す

株式会社富士通研究所 導入事例
富士通研究所は、所内共通クラウドの実現に向け、新しいネットワークのスイッチに富士通のコンバージドスイッチ「Brocade VDX series」を導入しました。回線の10G化により帯域不足を解消し、センタースイッチと回線の冗長化により可用性を向上。ストレージ統合を目的にFCoEの検証も開始。今後、論理スイッチによる一元管理を実現し運用管理コストの半減を目指しています。
[ 2013年10月23日掲載 ]
導入事例 株式会社富士通研究所 (869 KB)(A4・2ページ)
INDEX
| 国名 | 日本 |
|---|---|
| 業種 | ICT技術の研究開発 |
| ハードウェア | Brocade VDX 6710、Brocade VDX 6720、Brocade VDX 6730 コンバージドスイッチ
FUJITSU Storage ETERNUS DX ディスクアレイ FUJITSU Storage ETERNUS NR1000F ネットワークディスクアレイ |
「集約率、トポロジー構成の柔軟性、コンバージド・ネットワークにおける実績などから、Brocade VDX seriesを選択しました。運用管理の面ではスイッチの仮想化に注目しました。仮想的な1台の論理スイッチにより運用管理の負荷を大幅に軽減できます」
富士通グループの研究開発の中核を担う富士通研究所。同研究所はICTインフラの導入においても先進技術へのチャレンジを重視しています。現在、所内共通クラウドの実現に向けた取り組みを進めており、新ネットワークのスイッチに富士通のコンバージドスイッチ「Brocade VDX series」を採用しました。採用の理由は、集約率、トポロジーの柔軟性、コンバージド・ネットワークの実績などがポイントになりました。導入後、回線の10G化により帯域不足を解消し、センタースイッチと回線の冗長化により可用性を向上。またストレージ統合を視野にFCoEの試験運用も実施。今後、論理スイッチによりスイッチの一元管理を実現し、運用コストの半減を目指しています。
| 導入前の課題 | 導入による効果 | |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
導入の背景
所内共通クラウドの実現に向けてネットワークの見直し
ICTのパラダイムは、計算機中心からネットワーク中心、そして人間中心(ヒューマンセントリック)の時代へとシフトしてきています。富士通は、ICTが人の活動を自然にサポートし情報が新たな価値を生み出して持続的に成長できる社会を「ヒューマンセントリック・インテリジェントソサエティ」と呼び、その実現を目指しています。
富士通ビジョンの実現を先端技術の研究開発で支えているのが富士通研究所です。同研究所の研究領域は、五感インターフェースからクラウド、次世代ソリューション、大量データの利活用支援、デバイスや材料に至るまで多岐にわたっています。

株式会社富士通研究所
R&Dマネジメント本部
情報システム技術部
エキスパート
秋山 幸司 氏
先端技術の研究開発においてもICTの活用は不可欠ですが、一般企業の情報システム部門との違いもあります。「課題解決だけでなく、研究所の情報システム部門として新しい技術にチャレンジすることを求められています」と、R&Dマネジメント本部 情報システム技術部 エキスパート 秋山幸司氏は話します。
所内ICTインフラにおける現在の重点テーマは所内共通クラウドの実現です。「事務部門はもとより、研究部門が個別に導入していたICTリソースも含め、共通クラウド基盤に集約するという計画です。研究部門を資産管理や機器メンテナンスといった業務から解放するとともに、タイムリーなリソースの提供、効率的な設置・節電、研究所全体でのトータルコストの削減を目的としています」(秋山氏)。
所内共通クラウドの実現には、そのベースとなるネットワークの見直しが必要でした。
導入のポイント
集約率、トポロジー構成の柔軟性、スイッチの仮想化が採用のポイント
富士通研究所の国内拠点は川崎(本社)と厚木にあります。所内共通クラウドの取り組みは川崎拠点から行われ、ネットワークの見直しでは現状とクラウド化の2つの課題において解決が求められました。
現状の課題について「川崎拠点のネットワークは、端末の増加に伴い、検疫/MAC認証を行うエッジスイッチが急増しフロアスイッチを追加するなど管理が煩雑となり障害の影響範囲も拡大しました」と、R&Dマネジメント本部 情報システム技術部 マネージャー 若宮賢二氏は話します。

株式会社富士通研究所
R&Dマネジメント本部
情報システム技術部
マネージャー
若宮 賢二 氏
クラウド化の課題では、PCやサーバの搭載ポートが100Mから1Gにシフトしたことでフロアスイッチとセンタースイッチ間における帯域不足や、ネットワークの構成変更に伴うトラフィックの増加、ストレージ統合への対応が必要でした。
現状とクラウド化の課題を解決するためにスイッチの選定では、回線の10G化、冗長化、運用管理の効率化に加え、ファイバチャネルの統合を可能にするコンバージドスイッチもポイントとなりました。またコストを抑えるために既存のアクセス系の収容を前提としました。
複数社の製品を検討した結果、「集約率、トポロジー構成の柔軟性、コンバージド・ネットワークにおける実績などから、Brocade VDX seriesを選択しました。運用管理の面ではスイッチの仮想化に注目しました。複数のBrocade VDX seriesを仮想的な1台の論理スイッチとして使用できるVCS(Virtual Cluster Switching)機能を活用することで運用管理の負荷を大幅に軽減できます」(若宮氏)。
システムの概要
センタースイッチは「Brocade VDX 6720」2台でスイッチと回線を冗長化
2012年3月、製品納入後、情報システム技術部ではファブリックを組んで動作確認を開始。「ファブリックの構成はつなぐだけでOKと言えるほど簡単でした。負荷をかけても大きな問題は起きませんでしたが、コンバージドスイッチにふれるのは初めてだったこともあり慣れるのに多少時間はかかりました」(若宮氏)。
スイッチの置き換えは、2012年12月末の全館停電に合わせてセンタースイッチから行い、フロアにある集線スイッチは休日を利用して段階的に実施し2013年2月中旬に配備を完了しました。
新ネットワークは、センタースイッチに「Brocade VDX 6720」2台を採用しスイッチと回線の冗長化を図っています。サーバエリアのラック集線スイッチに「Brocade VDX 6730」、オフィスフロアのフロア集線スイッチに「Brocade VDX 6710」を採用しセンタースイッチとの間を10G回線で結び、集線スイッチの先に富士通製エッジスイッチがつながっています。センタースイッチを含む集線スイッチは20台以上、エッジスイッチは300台以上の規模の構成です。またBCP(事業継続計画)の観点から運用系ストレージのミラーを設置している遠隔地のセンターとも直結。
新ネットワークの設計の特徴について「所内共通クラウド化でサービスを提供する場合、事務部門と研究部門ではサービスレベルが異なることから事務系、研究系などネットワークを分けた運用を考えています。そのためサーバエリアやオフィスエリアに関わるL2はしっかりと固め、L3以上はあとで差し替えができるように分離しています」と秋山氏は話します。
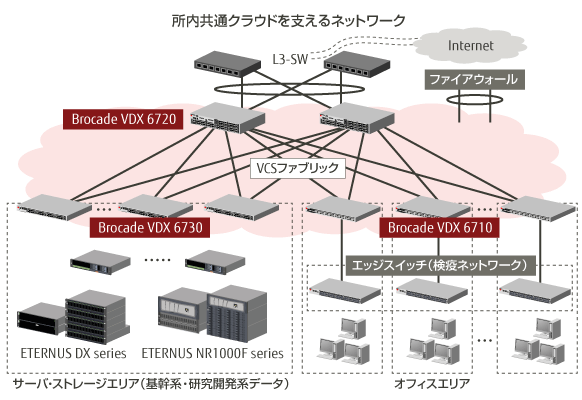
導入の効果と今後の展望
論理スイッチによる一元管理で導入・運用コストの半減を見込む
導入効果としては、回線の10G化によりクラウド化に伴う帯域不足が解消されました。また既存のシャーシ型のセンタースイッチに比べ、「Brocade VDX 6720」は二重化による2台を合わせた消費電力でも約2000Wの削減を実現しています。
運用管理の面では帯域に十分余裕があることから、所内で利用しているVLANをすべて通すという設定で共通化し運用の効率化を図っています。また工事費を抑えるべく物理トポロジーは従来のものを踏襲していますが、これまでとは異なり、局所的にトラフィックが増えたときにバイパスするための配線を追加し負荷分散することも容易です。
ストレージ統合に向け、FCoEは試験段階から実用段階に移り始めています。また、サーバは物理的な集約を行い、所内ハウジングを進めており、次のステップとしてサービス化に取り組むとともに、一部、物理サーバの貸し出しも検討中です。
今後の展望について「論理スイッチの試験運用を行いたいと考えています。従来、個別に管理していたスイッチを集約、一元管理を実現できることから、導入・運用コストの半減を見込んでいます。また厚木拠点への横展開も検討しています」と秋山氏は話します。 富士通研究所の所内共通クラウドが進展するほどに「Brocade VDX series」が果たす役割はますます重要になっていきます。
| 所在地 | (本社)〒211-8588 川崎市中原区上小田中4-1-1 |
|---|---|
| 代表取締役社長 | 富田 達夫 |
| 創設 | 1962年 |
| 資本金 | 50億円 |
| 従業員数 | 約1,250名(2013年5月1日現在) |
| 事業内容 | 次世代のソリューション/サービスやシステム、ネットワーク、デバイスや材料に至る先端技術の研究開発 |
| ホームページ |  株式会社富士通研究所 |
本事例中に記載の肩書きや数値、固有名詞等は掲載日現在のものであり、このページの閲覧時には変更されている可能性があることをご了承ください。なお、社名敬称は省略させていただいております。
製品情報

SANとLANを統合し、卓越した運用性と拡張性を提供
コンバージドスイッチ