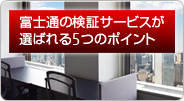「PRIMERGY」と「ETERNUS」を基盤に信頼性と拡張性の高いシステムを実現、イントラネットの新たな可能性を切り拓く
株式会社ベネッセコーポレーション様 導入事例
「イントラネットには常に、セキュリティの確保やTCOの削減、ユーザーの生産性向上という課題が突きつけられています。これらの課題を解決するには"過去のしがらみ"から脱却した新たなインフラが必要だったのです」

2009年7月17日掲載/ 印刷用 PDF版ダウンロード (831 KB)
| 導入事例概要 | |
| 業種: | サービス業(教育・出版・介護・通信販売) |
| ソリューション: | イントラネット |
| ハードウェア
ソフトウェア: |
ETERNUS4000 ディスクアレイ モデル500、PRIMERGY RX300 S4、PRIMERGY BX620 S3 |
「Benesse(よく生きる)」を企業理念に、一人ひとりのライフステージに合わせた多様なサービスを提供しているベネッセコーポレーション。ここでは1990年代後半に導入され、社内の情報発信や情報共有、電子メール基盤として活用されてきたイントラネットシステムが、全面的にリニューアルされました。以前は複数ベンダーの製品で構成されていたシステムをマイクロソフトテクノロジーへと統合、使用するソフトウェアも最新バージョンへとアップグレードしているのです。この環境を支えるハードウェアには「PRIMERGY」と「ETERNUS」を採用し、高い信頼性と拡張性を確保。富士通の技術力やサポート力、マイクロソフト製品に関する豊富なノウハウも積極的に活用することで、新環境へのスムーズな移行を実現しています。
| 導入前の課題 | 導入による効果 | |
|---|---|---|
| ハードウェアの老朽化やソフトウェアのバージョンが古くなることで、安定性やパフォーマンス、キャパシティに限界がきていた。 | 高信頼かつ拡張性の高いハードウェアを採用することで、安全性が高く、スケーラブルな基盤を確立できた。 | |
| 複数ベンダーの製品が混在しており、シングルサインオンの実現やユーザーの利便性向上、セキュリティ確保が難しかった。 | 大容量かつ高速なストレージによって、メールボックスの容量を大幅に拡大できた。 | |
| これらの諸問題を根本から解決するため、"過去のしがらみ"を断ち切った新たなインフラが求められた。 | 冗長化した新Exchange Serverへ移行することで、運用性と性能を同時に向上することができた。 |
導入の背景
老朽化・複雑化の問題を断ち切るためシステム基盤の刷新へ

1990年代半ばから普及が始まり、情報系システムの主役へと成長したイントラネット。現在では企業活動を支えるインフラとして、欠かせないものになっています。しかし10年あまりの間、次々と機能が追加された結果システムの複雑化が進み、運用性やセキュリティなどに問題を抱えるケースも増えてきました。また古いハードウェアの能力的な限界によって、ユーザーの利便性が制約されているシステムも珍しくありません。このような問題をイントラネットの全面的なリニューアルによって解決したのが、ベネッセコーポレーションです。
同社は電子メールシステムとしてMicrosoft Exchange Serverをバージョン5の頃に導入しており、2001年にはこれをExchange 2000 Serverへとアップグレードして使い続けています。しかしソフトウェアのバージョンが古くなったことや、ハードウェアの老朽化、複数のベンダー製品混在によるシステムの複雑化などによって、様々な問題が顕在化するようになっていたのです。
「まず複数のベンダー製品が存在することで、製品に関するサポート窓口が統一できないという問題がありました」というのは、ベネッセコーポレーションIT戦略部でイントラ基盤開発課 課長を務める鉢蝋吉久氏。そのため障害発生時の対応に時間がかかってしまったり「製品同士の相性の問題」といわれることもあったといいます。また同じイントラ基盤開発課の別所恵子氏は「メールボックスの容量制限や性能の限界も大きな問題になっていました」といいます。
「イントラネットには常に、セキュリティの確保やTCOの削減、ユーザーの生産性向上という課題が突きつけられています。これらの課題を解決するには"過去のしがらみ"から脱却した新たなインフラが必要だったのです」と鉢蝋氏。
導入のポイント
無停止稼働は必須条件、技術力やサポート力も重視

ベネッセコーポレーションでイントラネットのリニューアル検討が始まったのは2006年。その翌年には「ベネッセイントラ2008 プロジェクト」として、具体的な取り組みがスタートします。まずActive Directoryを最新のものにバージョンアップすると共に、クライアントPCのOSもWindows XPからWindows Vistaへとアップグレード。
さらに電子メールもExchange 2000 ServerからExchange Server 2007へとアップグレード。ひとりあたりのメールボックス容量も、50MBから1.5GBへと大幅に拡張することになりました。
もちろんこのような環境を支えるには、ハードウェアにも高い要求が突きつけられます。ベネッセコーポレーションはこのプロジェクトの実現にあたり、複数ベンダーからの提案を比較検討。その結果、サーバーにPRIMERGY、ストレージシステムにETERNUSを採用した富士通の提案を選択するのです。
「ハードウェア選定で最も重視したのは信頼性です」と鉢蝋氏。無停止で動き続けることは最も基本的な要件だったと振り返ります。「当社のユーザー数は約3000名ですが、富士通が提案したシステム構成にはすでに同じ規模の実績があり、安心して導入できると判断しました」その一方で「マイクロソフト製品に関する経験やインテグレーション能力、サポート力も重要でした」というのは、シンフォーム テクニカルサービス部 課長を務める吉田秀史氏。同社はベネッセグループのIT企業であり、今回のプロジェクトでもプロジェクト全体の計画立案やマネジメント、移行作業などを担当しています。「富士通とは以前からもお付き合いがあり、ハードの信頼性もさることながら、サポート力についても高く評価しています。何かあれば、すぐに本社のある岡山まで来てくれるなど、非常に心強いパートナーです」シンフォームと富士通の参画のもと、システムのリニューアル作業が始まった のは2007年6月。まずActive Directory 2003が導入され、クライアントPCのOSアップグレードとドメイン移行が2008年3月までかけて進められていきました。2008年7月にはメール環境の切り替えを実施し、新たなイントラネット環境が完成するのです。
システム概要
安全性と拡張性・性能を強く意識、投資効果の最大化にも配慮
システム構成は図に示す通り。メールサーバーにはラックマウント型のPRIMERGY RX300 S4を採用し、フロントエンドは負荷分散、バックエンド(メールボックス)は4ノードクラスター(3 アクティブ/1 パッシブ)で冗長化されています。ポータルサーバーにはブレード型のPRIMERGYBX620 S3を採用、フロントエンドは同じく負荷分散、バックエンドは1 アクティブ/1 パッシブのクラスターで冗長化されています。ストレージシステムにはETERNUS4000 モデル500を採用。メールボックスやポータルのコンテンツ、さらにバックアップの領域も確保されており、総容量は数十TBに達しています。
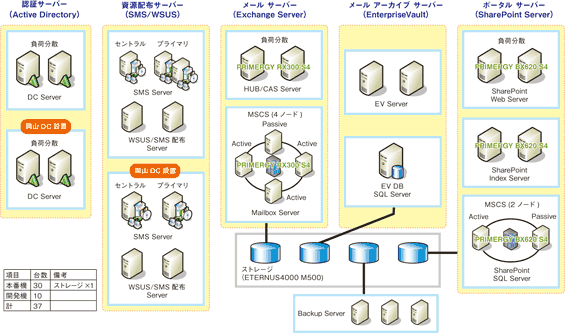
「このシステムは安全性だけではなく、拡張性や性能も強く意識した構成になっています」と説明するのは、シンフォーム テクニカルサービス部 業務基盤サービスセクションで係長を務める佐藤弘一氏。すでにユーザー数4000名を視野に入れたサイジングを行っていますが、それ以上でも同一インフラで対応できるはずだといいます。その一方で「安全性と投資のバランスにも配慮しました」というのは、システム設計に参画した富士通ソフトウェアテクノロジーズでプロジェクト課長を務める奥和寿。その結果は鉢蝋氏からも「他社の提案に比べて高い費用対効果が実現されています」と評価されています。
富士通の技術力やサポート力は、移行計画の立案や実施でも大きな貢献を果たしています。例えば今回のExchange Serverの移行では、環境混在によるユーザーの利便性低下を回避するため、新旧バージョンの並行稼働を行わずに一気に切り替えることが求められました。「これはハードルの高い要求ですが、富士通はマイクロソフト製品に関する豊富なノウハウを活かし、移行方法を一緒に考えてくれました」と佐藤氏は振り返ります。
また佐藤氏と同じセクションに所属する松本憲英氏は「Exchange メールデータの移行も、富士通による事前検証によってスムーズに進みました」と指摘。今回、岡山の旧Exchange Serverにある一人当たり50MB×数千人のメールボックスを多摩データセンターの新Exchange Serverへ移行する作業が、わずか3日間で終了したといいます。
導入効果と今後の展開
過去のしがらみからの脱却に成功、今後は社外との情報共有も
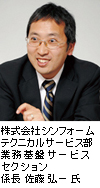
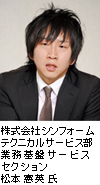
新しい環境にイントラネットを移行したことで、システムの信頼性は大きく向上しました。「これまで計画停止以外のサーバー停止は発生していません」と佐藤氏。また計画停止を行う場合でも、冗長化されたシステム構成によって、最小限の停止時間で済むようになったといいます。システムが安定稼働することで管理工数も削減。またアーカイブ機能を活用することで、コンプライアンス対策の実施も容易になりました。
Exchange Server移行後に導入したポータルサーバーにブレード型を採用した点も高く評価されています。
「実はベネッセグループでは2008年夏にグリーンITの方針が打ち出されたのですが、富士通はその後に導入されるサーバーの提案を即座にブレード型へと切り替え、この方針に合わせてくれました」と鉢蝋氏。今後はブレード型サーバーの適用領域を拡大すると共に、OSのバーチャル化なども進めていきたいといいます。
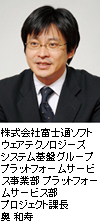
もちろんユーザーにとっての利便性も向上しました。メールボックスの容量が大幅に拡大され、シングルサインオンも実現されたからです。「今ではPCにサインオンすれば、すべての情報へシームレスにアクセスできます」と鉢蝋氏。また別所氏は「アクセス権限がActive Directoryにより一元管理できるため、セキュリティも高まりました」といいます。
今後は社内だけではなく、グループ企業との情報共有基盤としても、このイントラネットを活用する計画だといいます。さらに次のステップでは、グループ外の協力企業との情報共有を実現することも検討されています。
ベネッセコーポレーションは最新のインフラによって"過去のしがらみ"を断ち切ることで、イントラネットの新たな可能性を切り拓くことに成功しているのです。
株式会社ベネッセコーポレーション様 概要
| 創業 | 1955年1月28日 |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役会長兼CEO 福武 總一郎 |
| 本社所在地 | 岡山県岡山市南方 3-7-17 |
| 事業内容 | 教育、語学、生活、介護に関する商品・サービスの提供 |
| 資本金 | 136億円 |
| 従業員数 | 3,078名(2008年4月1日現在) |
| URL | http://www.benesse.co.jp/ |
本事例中に記載の肩書きや数値、固有名詞等は掲載日現在のものであり、このページの閲覧時には変更されている可能性があることをご了承ください。