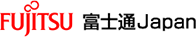企業成長を加速するカーボンニュートラル戦略と実践のポイント
カーボンニュートラルは、単なる環境対策ではなく、企業の持続的な成長を支える重要な戦略のひとつです。脱炭素社会の実現に向けた取り組みは、規制強化への対応だけでなく、競争力の向上や市場での信頼獲得にも直結します。本記事では、企業がカーボンニュートラルの実現に向けて取るべき具体的な方策について解説します。補助金や税制優遇制度を活用しながら、成長戦略として脱炭素経営を推進するためのポイントを把握しましょう。
カーボンニュートラルが企業成長に不可欠な理由
近年、脱炭素を推進する企業が市場での優位性を高める傾向が顕著になっています。消費者や投資家の意識が高まり、ESG経営の評価基準が強化されるなか、サステナビリティを経営に組み込むことは、競争力の強化にもつながります。また、省エネ技術の導入やクリーンエネルギーの活用によるコスト削減、ブランド価値の向上、グローバル市場での信頼獲得といったメリットも期待できます。
カーボンニュートラル実現に向けた戦略的アプローチ
カーボンニュートラルの実現には、長期的なビジョンの設定と具体的な計画の策定が必要です。まず、企業は排出量の可視化と削減計画の立案を進め、短期・中期・長期のロードマップを構築することが重要です。さらに、ITツールを活用したデータ管理や、エネルギー効率の向上、サプライチェーン全体での脱炭素化など、多角的なアプローチを取ることで、より効果的な脱炭素経営が可能となります。これらの取り組みを支援する補助金や税制を活用しながら、コストを抑えつつ成長につなげる戦略を推進することが求められます。
2050年カーボンニュートラルに伴う日本のグリーン成長戦略
日本は、2020年10月に2050年カーボンニュートラルを目指すことを宣言しました。2020年12月には、カーボンニュートラルの達成に向けて「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」を発表しました。グリーン成長戦略は、カーボンニュートラル実現のために、経済と環境の好循環を作るための産業政策や、成長が期待できる産業分野の実行計画をまとめたものです。
14の産業分野
グリーン成長戦略では、今後の成長が期待される14分野の産業に対して目標が設定、実行計画の策定がされ、国の施策支援も集中させています。
14の産業分野は以下のとおりです。
「エネルギー関連産業」
- 洋上風力・太陽光・地熱産業(次世代再生可能エネルギー)
- 水素・燃料アンモニア産業
- 次世代熱エネルギー産業
- 原子力産業
「輸送・製造関連産業」
- 自動車・蓄電池産業
- 半導体・情報通信産業
- 物流・人流・土木インフラ産業
- 食料・農林水産業
- 航空機産業
- カーボンリサイクル・マテリアル産業
「家庭・オフィス関連産業」
- 住宅・建築物産業・次世代電力マネジメント産業
- 資源循環関連産業
- ライフスタイル関連産業
カーボンニュートラルに取り組むための補助金・制度の有効活用
カーボンニュートラルは自社の成長戦略のためにも重要です。そのための一助となる補助金や投資促進税制があります。ここでは、カーボンニュートラルで使える補助金や投資促進税制について解説します。
補助金
カーボンニュートラルへの社会的な関心や注目度の高まりに比例するように、カーボンニュートラル関連の事業を推し進める企業を支援する補助金や助成金の数は増加中です。国は、カーボンニュートラル関連の補助金事業を数多く設けています。企業活動におけるカーボンニュートラル実現のために、補助金や助成金の制度を積極的に活用しましょう。
カーボンニュートラルの取り組みを支援する補助金や助成金の例は、以下の通りです。
- 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金
- 民間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業(一部 総務省・農林水産省・経済産業省 連携事業)
- 業務用建築物の脱炭素改修加速化事業
投資促進税制
カーボンニュートラルに向けた投資促進税制は、カーボンニュートラルへの投資を促進する目的で設定された制度です。企業が、カーボンニュートラル化効果が高い製品の開発や購入、エネルギー消費量の削減となる設備投資などを行う際に、税制優遇を受けられます。企業の規模により控除割合は異なりますが、最大10%の税額控除が受けられます。
また、補助金との併用も可能です。なお、控除税額、DX投資促進税制と合計で法人税額の20%までです。控除の対象となるのは、産業競争力強化法に基づいて、事業適応計画(エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画)を作成し、事業所管大臣の認定を受けた事業者です。環境配慮企業、中小企業ともに、業種や資本金の規制なく、申請が可能です。
カーボンニュートラルに関する補助金・助成金が使える具体的な取り組み
助成金や補助金を利用するために、どのように目標を設定すべきか、目標達成のためにどのように進めていくとよいか具体的な取り組みを解説します。
二酸化炭素削減目標と計画の設定
2024年現在、企業に対して二酸化炭素削減を求める動きは当たり前になっています。世界中の大手企業が二酸化炭素削減に注力しています。企業が二酸化炭素削減の目標と計画を設定する際は、パリ協定に基づく「SBT(Science Based Targets)」の目標を参考に、5〜15年後の二酸化炭素削減達成計画を立てましょう。
SBT(Science Based Targets)とは、パリ協定が求める水準と整合した、企業が設定する温室効果ガス排出削減目標のことです。SBTをもとに、二酸化炭素削減達成目標と計画を設定した企業は、気候変動への取り組みを公表することで、一般社会や投資家からの信頼を得やすくなります。
ITツールの導入
カーボンニュートラルの推進には、ESGデータ管理や二酸化炭素排出量の可視化が不可欠であり、ITツールの導入が有効です。
企業は、排出量の測定・分析・管理を効率化し、データの精度を向上させることで、環境対策の効果を正確に把握できます。特に、CDPやTCFDなどの開示要件に対応するためには、サプライチェーン全体の排出データを集約し、透明性のある情報開示が求められます。また、Scope1・2・3の排出量をリアルタイムでモニタリングし、削減計画の策定や進捗管理を強化することも重要です。これらのシステム導入にはコストがかかるため、「省エネルギー投資促進事業費補助金」や「カーボンニュートラル投資促進補助金」などの支援制度を活用し、負担を軽減することが推奨されます。
省CO2設備(再生可能エネルギー・CO2改修処分技術など)の導入や更新
高効率設備を導入したり、電化・燃料転換を行ったりすることで、工場や事業場における二酸化炭素の排出量を効率的かつ、大幅に削減できます。省CO2設備の例には、窓の二重化、屋根の高断熱化、高効率空調設備などが挙げられます。
まとめ
カーボンニュートラルの実現には、補助金や税制を活用しながら、計画的かつ具体的な取り組みを進めることが重要です。企業は、二酸化炭素削減目標の策定やESGデータ管理、排出量の可視化を通じて、自社の環境負荷を正確に把握し、戦略的に削減を進める必要があります。そのためには、ITツールの導入や省CO2設備の更新を積極的に行い、エネルギー効率の向上を図ることが求められます。
さらに、「省エネルギー投資促進事業費補助金」や「カーボンニュートラル投資促進補助金」などの支援制度を活用することで、初期投資の負担を軽減しながら脱炭素経営を推進できます。また、カーボンニュートラルに向けた投資促進税制を活用し、税制優遇を受けることで、より積極的な設備投資や技術開発が可能となります。
カーボンニュートラルへの取り組みは、単なる環境対策にとどまらず、企業の成長戦略の一環として競争力の強化や市場優位性の確立につながります。補助金や税制を活用しながら、計画策定やツール導入を進め、持続可能なビジネスモデルを構築していくことが、今後の企業経営において不可欠となるでしょう。
-
WEBでのお問い合わせはこちら入力フォーム
当社はセキュリティ保護の観点からSSL技術を使用しております。
-
お電話でのお問い合わせ
富士通Japanお客様総合センター
0120-835-554受付時間:平日9時~17時30分(土曜・日曜・祝日・当社指定の休業日を除く)