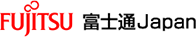なぜ企業はカーボンニュートラルを急ぐべきなのか?取り組むメリットとScope3の必要性
パリ協定を契機に社会的にカーボンニュートラルへ取り組む動きが加速している中、環境へ配慮する企業も増えてきております。今、企業がカーボンニュートラルに取り組むメリットと共に、Scope3対応の必要性についても解説いたします。
環境への取り組みが消費者や取引先に評価される時代が到来
企業が環境問題にどれだけ取り組んでいるか、その取り組みの進み具合が消費者や取引先などステークホルダーから評価される時代が到来しました。温室効果ガス排出量の算定・開示については、ほとんどの企業でおおむね一巡したきらいがあります。そこで、市場や投資家などのステークホルダーからは、経済成長と関連したカーボンニュートラル化の取り組みを重視する声が上がっています。
各企業は、2050年カーボンニュートラルをただ漠然と目指したり、目標に掲げたりするだけでは、ステークホルダーに背を向けられかねません。環境問題と経済成長を両立させながら、カーボンニュートラルに向けた舵取りが求められています。
企業価値の向上とサプライチェーン全体での取り組み
2015年に採択されたパリ協定をきっかけに、企業には気候変動や気温上昇に対応した経営戦略の開示(TCFD)やカーボンニュートラルに向けた目標設定(SBT、RE100)を提示することが求められるようになりました。企業のカーボンニュートラル経営への取り組みは、ESG投資が国際的なトレンドである現代において、企業価値の向上につながることが期待できます。
また、カーボンニュートラル経営において、企業は環境問題や持続可能性への配慮を経営の主軸に置き様々な取り組みを進めています。しかし、今日の環境問題の解決には、自社のみならず、自社以外のサプライチェーンの協力が必要です。サプライチェーン全体で積極的に環境配慮の視野を拡げていくことが求められているのです。
COP26の目標実現とScope3対応
環境配慮企業がサプライチェーンの取り組みを求める背景には、COP26(国連の第26回気候変動枠組み条約締約国会議)で、以下の目標が提示されたことがあります。
- 「産業革命からの世界の平均気温の上昇を1.5度以内」に抑える
目標実現のためには、温室効果ガスの間接排出を指すScope3への対応を進めなくてはなりません。
また、環境配慮企業はサプライチェーン全体でのCO2排出量算定のために、取引先にもカーボンニュートラルの取り組みを求める動きが加速しております。取引先として評価されるためにも、Scope3への対応が必要となってきております。
Scope3とは
Scope3とは、事業者が自ら排出している温室効果ガスのうち、Scope1、Scope2以外の事業者の活動に関連する他社の温室効果ガスの排出量のことです。Scope1、Scope2、Scope3の概要は以下のとおりです。
- Scope1:Scope2以外の事業者の活動に関連する他社の温室効果ガスの排出量
- Scope2 : 他社から供給された電気、熱・蒸気の使用に伴う間接排出
- Scope3 : Scope1、Scope2以外の間接排出
サプライチェーン排出量は、Scope1排出量+Scope2排出量+Scope3排出量を加算したものです。
Scope3対応が必要な理由
企業活動に伴う温室効果ガス排出量の範囲は、自社だけではありません。サプライチェーン全体での排出量を算定し、正確な算出が求められています。そのため、サプライチェーンを構成する事業者がそれぞれ協力し、温室効果ガスの削減対策を効率的に進めなければなりません。Scope3の算出が求められるなかで、カーボンニュートラルの動きに対応できない企業は、淘汰される時代がやってきています。
グローバル市場における製造業の動き
Appleをはじめとする海外の環境配慮企業のなかには、サプライチェーンに対してカーボンニュートラルの取り組みを要求し始めています。カーボンニュートラルに対応しない企業は、サプライチェーンのネットワークから除外される可能性が出てきています。
これらの影響が及ぶ範囲は、環境配慮企業の本社がある国に限りません。日本の製造業を牽引するグローバル企業にとどまらず、グローバル企業のサプライヤーである日本国内の製造業も対応が必要となってきます。
海外のカーボンニュートラル政策に対応する必要がある
EUや米国カリフォルニア州、中国などでは、カーボンニュートラルにかかわる法律や制度、ルールが整備されています。これらの動きが、非課税措置の適応を受けることを難しくする要因となることもあります。日本の政策如何にかかわらず、海外のカーボンニュートラル政策の動きに先手をとって対応する必要があるでしょう。
また、国際サステナビリティ基準審議会(ISSB) が、Scope3の開示を求めるIFRSサステナビリティ開示基準(ISSB基準)を公表したことで、Scope3の開示がよりグローバルスタンダードになってきております。そして、日本でも民間のサステナビリティ基準委員会 (SSBJ) により日本版の基準策定を進めており、今後義務化される可能性が出てきております。
Scope3排出量を算定するメリット
Scope1、2排出量とあわせて、Scope3排出量を算定することで、サプライチェーン排出量を正確に把握できます。組織のサプライチェーン上の活動に伴う排出量を算定することは、企業活動全体を管理することにもつながります。
Scope3の排出量は、一般的に企業全体の排出量の大半を占めます。そのため、サプライチェーン排出量を開示し、削減を進めることは、企業にとって温室効果ガス排出量の削減に大きなインパクトを与えるでしょう。サプライチェーンの排出量を算定するメリットを解説します。
削減対象が特定できる
サプライチェーン排出量の総量や排出源ごとの排出割合を把握することで、サプライチェーン上で、優先的にScope3の排出量の削減すべき対象を特定できます。
環境経営指標に活用できる
自社のサプライチェーン排出量の経年変化を把握することで、削減対策の進捗状況の確認が可能です。これを活用し、環境経営指標や環境配慮企業としてのプロモーションに生かせるでしょう。
事業者間での排出量算定連携による更なる削減
排出量算定のための情報交換の場を設けることで、サプライチェーン上の他事業者と連携することによる温室効果ガスの削減が期待できます。
投資家からの評価向上に繋がる
昨今、サプライチェーン排出量に関する質問を、投資家や環境格付機関などが聞いてくる傾向にあります。サプライチェーン排出量を正確に把握することで、これらの質問に適切に回答できるようになるため、自社の評価を高められるようになります。
CSR情報のひとつとして提示できる
企業の社会的責任情報開示の一環として、サプライチェーン排出量をCSR報告書、Webサイトなどに掲載し、自社の取り組みを積極的に発信することで、自社の環境活動への理解・企業評価が高まります。
まとめ
企業はカーボンニュートラルへの取り組みを急ぐことで、取引先や消費者の評価を高め、競争力を維持できます。海外や日本の政策対応を見据え、先手のカーボンニュートラル対策が必要です。また、Scope3の排出量を正確に把握し、削減の進捗を示すことで、環境配慮企業としての信頼を獲得し、取引継続や企業価値向上につながります。
併せて、投資家や消費者、金融機関などのステークホルダーから評価されるためには、経済活動と並行しながら環境問題に取り組むことが重要です。サプライチェーン全体の温室効果ガス排出量を正確に算出し、優先してScope3の排出量の削除すべき対象を明確にし、削減対策の進捗状況の経年変化を把握し環境経営指標に活用しましょう。
- ダウンロードはこちら
ホワイトペーパー:Scope3算出の障壁と企業が直面する課題
(注)資料のダウンロードにあたり、簡単な登録が必要です。
-
WEBでのお問い合わせはこちら入力フォーム
当社はセキュリティ保護の観点からSSL技術を使用しております。
-
お電話でのお問い合わせ
富士通Japanお客様総合センター
0120-835-554受付時間:平日9時~17時30分(土曜・日曜・祝日・当社指定の休業日を除く)