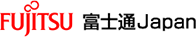成長を支えるESG経営~その重要性と実践ポイント~
社会的意識の高まりとともに、企業の社会貢献や持続可能性が投資家や消費者から重視されるようになりました。企業は、長期的に利益を上げるだけでなく、社会的責任を果たすことも求められています。ESG経営は、もはや企業経営における必須要件となりつつあります。 そこで今回は、ESG経営が企業経営の基礎的な要因となっている背景、そして、ESG経営を実践するためのポイントについて解説します。
ESG経営が注目されている理由
ESG経営は、企業の環境・社会・ガバナンスへの取り組みを評価軸とする経営戦略として、注目を集めています。
ESG経営が注目を浴びる背景として、ESG投資の普及、金融業界に向けたPRIなどが挙げられます。
ESG投資が世界的に急速に普及している
ESG投資とは、環境、社会、ガバナンスの3つの基準を踏まえたうえで、投資対象を選定する手法です。財務的なパフォーマンスだけでなく、社会的、環境的な影響も評価の対象となります。ESG投資は、今世界で急速に発展しています。
その理由として挙げられる要因が、投資家の意識の変化です。投資家が、ただ単純に利益を追求する時代は終わろうとしています。現在、投資家は、持続可能性や社会的影響を重視して投資先を決めるようになっています。多くの投資家は、ESG基準を満たす企業が長期的に安定したリターンを提供してくれる、社会的なリスクに対して耐性があると考えています。
金融業界に向けたPRIが重視されている
世界的な喫緊の課題である気候変動への対策として、金融業界では「PRI(責任投資原則)」が特に重要視されています。ESG経営におけるPRIとは、国連が金融業界に向けて提唱した行動原則です。
国連は、環境(Environment)社会(Society)ガバナンス(Governance)の3つの要素(ESG)を投資に組み込むことを求めました。この行動原則のなかで、投資家は、積極的に責任ある投資を推進するための行動を取るように提示しています。
PRIの目的
PRIは、投資におけるリスク管理の重要な視点です。PRIの目的は、持続可能な社会の実現です。投資家が投資を判断する過程として、ESG投資を意識することで長期的な視点で、財務的責任と社会的な責任を果たすことを目指しています。
多様化する経営リスクに対応するため
多様化する経営リスクに対応するためにも、ESG経営は重要です。現在、ビジネス界はVUCA時代を迎えています。VUCAとは、Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)の頭文字を取った言葉で、現代のビジネス環境の不安定さと予測困難さを表します。
環境問題、社会問題は規模が大きく、事業の存続にも大きく影響します。ESG経営に取り組み、管理体制づくりや情報の開示と保護、法令遵守に力を入れることは、管理体制の整備とリスクの軽減につながります。
SDGs
SDGs(持続可能な開発目標)は、経済・社会・環境の3つの側面のバランスが取れた社会を目指す世界共通の目標です。現在、各国はこの目標を達成するためにさまざまな取り組みを行っています。また、SDGsの認知度が上がるにつれ、政府だけでなく企業や個人でも意識する人々が増加しました。SDGsへの意識の向上に伴い、ESG経営への注目度も高まっています。
企業にはCDP対応が求められている
SDGsの達成にも関連し、近年、企業の環境対策を評価する指標としてCDPが注目を集めています。
CDPとは、「気候変動」「フォレスト」「水セキュリティ」の3つの質問書を通じて環境問題への取り組みに関する情報を収集することです。質問書は、企業が投資に値する気候変動対策を実施しているかを示すもので、 TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)とも内容が整合しています。
CDPでは、質問書に対する回答をもとに、企業を8段階のスコアで評価します。CDPのスコアは、企業を評価するための重要な指標となっており、高いスコアを獲得することは、資金調達や企業価値向上に繋がります。投資家に評価され、投資先として選ばれるために、CDP対応が求められています。
TCFDの賛同
気候変動の抑制には、企業の役割が不可欠です。企業には、気候変動によるリスクや影響を考慮し、どのような対処をすべきか、事前にシミュレーションしたうえでの経営戦略が求められています。日本ではコーポレートガバナンスコードでの義務化により、プライム市場の企業はほとんど開示をしていますが、企業の状況に応じて常にブラッシュアップする事が必要です。
企業がESG経営に取り組むうえで、TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)に賛同することは重要な要素です。TCFDに賛同することで、企業は気候変動対策を提示できるため、投資家へのアピールにつながります。TCFDでは、具体的に以下の4つの項目について開示するように定めています。
- ガバナンス:気候関連のリスクと機会に関する組織のガバナンスを開示する
- 戦略:気候関連のリスクと機会が組織の事業、戦略、財務計画に及ぼす実際 の影響と潜在的な影響について、その情報が重要な場合は開示する
- リスク管理:組織がどのように気候関連リスクを特定・評価し、マネ ジメントするのかを開示する
- 指標と目標:気候関連のリスクと機会を評価し、マネジメントするために使用される測定基準(指標)とターゲットを開示する
日本は、2018年にTCFDに賛同し、2023年10月12日時点で1,470社がTCFDの賛同を表明しています。
ESG第三者保証獲得に向けた対応
ESG第三者保証獲得に向けた動きも活発化しています。サステナビリティ情報に関連する第三者保証を実施する企業は、年々増加しています。第三者保証を獲得するためには、自社のデータに対して、客観的な検証を受けなければなりません。第三者保証の基準として、ISSA5000、ISO 14064-3、PAS 2060などが挙げられます。
2028年以降、時価総額3兆円以上の企業に対し、第三者保証を義務化する案が検討されています。2030年代には、プライム上場企業にまで、その範囲が広がるのではないかと考えられています。
第三者保証の需要が高まっている背景
近年、企業のESGデータの信頼性が問われ、第三者保証の需要が高まっています。自社発信の情報だけでは信頼性が不足する場合があり、データの不整合や「グリーンウォッシュ」(実際には環境に貢献していないにもかかわらず、環境配慮をしているように見せかける行為)への懸念が高まっています。さらに、ESG規制の強化により、透明性が求められています。企業は、第三者保証を導入することで信頼性を確保し、投資家や消費者の支持を得ることが不可欠となっています。
第三者保証獲得のために企業は何をすべきか
第三者保証を受けるために、企業はデータへの正確性や品質などを担保、管理することが求められます。
データの正確性や信頼性を担保する
企業には、自社が提示するデータに対する正確性や信頼性を担保することが求められています。そのためには、データの品質を管理し、健全性を維持することが重要です。
データの品質を管理する
データの正確性、一貫性、完全性、信頼性の基準を設けましょう。そのためには、データの収集から分析までの過程を整備することが重要です。
データの健全性を維持する
データの健全性を維持するために、データの所有権やアクセス権、構造、品質管理、セキュリティなどの基準を定めましょう。収集したデータの信頼性を検証し、必要に応じて修正または削除します。
開示したデータが要件を満たしているか、ルールに沿っているかの確認も欠かせません。データの安全性を確保するために、適切なユーザーのみがアクセスできるよう対策を練りましょう。
ESG経営に取り組む企業の例
ESG経営に、さまざまな企業が取り組んでいます。
日鉄ソリューションズ
製造業や流通業などの支援に取り組む日鉄ソリューションズでは、ESG経営に取り組んでいます。
- TCFDへの賛同、温室効果ガス削減、循環型社会構築などに注力する
- 経済活動と環境保全の両立を目指し、データセンター運用や気候変動監視などの取り組みを展開する
- 社会的課題の解決を目指し、働き方改革、健康経営、品質管理の強化を推し進める
- プロジェクトリスク管理や品質管理を徹底する
- 「グローバル・ビジネス・コンダクト」を通じて、すべての人権を尊重する
キヤノン株式会社
医療機器、半導体などの製造を行うキヤノン株式会社の、ESG経営の取り組み例は以下のとおりです。
- 省エネルギー化の推進、再生可能エネルギーの利用などを推進し、2050年までに製品ライフサイクル全体でCO2排出量をゼロにする
- 人権についての懸念を通報できる内部通報窓口を国内外で設置する
- 男性の育児休業取得率を50%以上にする
- コーポレート・ガバナンス、リスクマネジメント、知的財産マネジメント、ブランドマネジメントの4つに分け、自社の考えを提唱する
まとめ
社会・環境・ガバナンスに配慮したESG経営が求められている背景には、企業の環境問題への対応や社会的責任が重視されていることが挙げられます。リスクを見据えた長期的かつ持続可能な経営や社会に配慮した企業活動が期待できるか否かが、投資家や消費者から重視されるようになったことも大きな要因です。
今後、企業はCDP対応、TCFD賛同、ESG 第三者保証獲得が必要となるでしょう。自社の取り組みを明確にし、正確かつ信頼のおけるデータの担保や品質の管理にも取り組むことが重要です。
- ダウンロードはこちら
ホワイトペーパー:全社戦略と連携したESG経営の推進
(注)資料のダウンロードにあたり、簡単な登録が必要です。
-
WEBでのお問い合わせはこちら入力フォーム
当社はセキュリティ保護の観点からSSL技術を使用しております。
-
お電話でのお問い合わせ
富士通Japanお客様総合センター
0120-835-554受付時間:平日9時~17時30分(土曜・日曜・祝日・当社指定の休業日を除く)