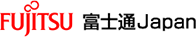脱炭素時代が到来!企業がいま直面する課題と取り組み事例
企業は今、消費者、政府、取引先、投資家などから、カーボンニュートラルに向けてどのような対応をするのか注目を浴びています。環境問題への取り組みは、国や政府が先導する時代から、環境配慮企業が率先して取り組む課題へと変わりつつあります。なぜ今、企業が環境問題に取り組むべきなのか、その理由と世界的企業の取り組み事例について解説します。
脱炭素時代とは
脱炭素時代とは、二酸化炭素(CO₂)などの温室効果ガスの排出を削減し、最終的にはゼロにすることを目指す時代のことです。
その契機となったのが、2015年COP21パリ協定採択です。ここで、世界の主要国の多くがカーボンニュートラルに向けた取り組みを進めました。
日本では、2017年にリコーが、将来的に再生可能エネルギー使用率100%を目指すことを宣言したことをきっかけに、カーボンニュートラルへの取り組みが本格化しています。
投資家や取引先、消費者、政府などからの環境配慮への期待が高まっている現状
現在、国内外の多くの企業が、カーボンニュートラル実現に向けた課題に直面しています。例えば、製造業においては工場設備のCo2排出量の可視化、省エネ対策などが挙げられます。
同時に、投資家や取引先、消費者、政府などからの環境配慮への期待が高まっています。政府は、EUが「国境炭素税」を開始する2026年から、カーボンニュートラルへの取り組みを加速すると宣言しています。また、投資家が気候変動をチャンスととらえる動きも出てきています。
カーボンニュートラルへの取り組みを避けられない理由
環境に対する社会的な関心が高まったことにより、企業はカーボンニュートラルへの取り組みが避けられない状況となっています。ESG投資の拡大や、排出量取引制度、炭素税といった制度の導入など、企業を取り巻く環境は大きく変化しています。ここでは、カーボンニュートラルに取り組むべき理由を、投資と環境問題の2つの側面から解説します。
ESG投資の拡大
環境配慮活動などの企業の社会的責任に基づいた活動に取り組む企業が増えるとともに、投資家や金融機関は、投資先を決める判断材料として、環境配慮や社会的側面を意識し始めました。ここで、注目されているのが、環境(Environment)、社会(Society)、企業統治(Governance)に着目したESG投資です。
ESG投資は、欧米で急速に拡大している現状があります。その理由として、ESG投資はESGを考慮していない場合よりも良好なパフォーマンスが発揮されるという結果が多数得られているレポートが発表されたことが挙げられるでしょう。
2022年の世界全体のESG投資額は約4,500兆円(30.3兆ドル)で、世界全体の投資額に占める比率は約24.4%です。米国・ブルームバーグ社の分析によると、2025年までに世界のESG資産は53兆ドルを超える見込みです。
投資家は、企業の安定した成長にESGが必要だと考えています。カーボンニュートラルはESG投資の拡大と密接な関係にあり、投資家はESG投資が、企業の持続的な経済成長を促し、ひいては、投資家への長期的なリターンを生み出すと考えています。投資家の環境や社会の問題への関心が増えたことにより、企業はカーボンニュートラルへの取り組みを余儀なくされているといえるでしょう。
排出量取引制度や炭素税への対応が避けられないため
環境問題への取り組みとして、排出量取引制度や炭素税があります。これらの国としての取り組みも、企業がカーボンニュートラルに取り組むべき要因となっています。企業はこれらの制度を理解し、適切な対応策を講じる必要があります。
排出量取引制度
排出量取引制度は、環境規制の強化制度の1つです。企業ごとの温室効果ガスの排出量に枠を設定し、その枠の過不足を企業間で取引します。排出量取引制度では、一定規模以上の二酸化炭素を排出する企業に対して、排出削減の取り組みを促す仕組みが作られています。
国や企業によって量が異なる温室効果ガスの排出量や削減余力を取引することで平準化し、全体で温室効果ガスの排出量を削減していくことが排出権取引のねらいです。なお、日本では、国単位では導入しておらず、東京都や埼玉県など一部の都道府県が都道府県単位で導入している状況です。
経済産業省は、2026年度に本格的に排出量取引制度を導入することを公表しました。年間10万トン以上の二酸化炭素を排出する企業の参加を義務付ける方針を固めています。対象となる企業は300〜400社に上ると考えられ、対象企業が排出する二酸化炭素の排出量は、国内の温室効果ガス排出量の6割近くを占めるといわれています。
炭素税
炭素税は、燃料や電気の使用といった二酸化炭素排出量に見合った税金をかける制度です。現状、日本では2012年に導入された地球温暖化対策税が実質的な炭素税といえるでしょう。地球温暖化対策のために、二酸化炭素排出量1トンあたり289円となるよう、化石燃料それぞれに対して税率が設定されています。これにより、2600億円程度の税収が見込まれています。
環境省は、2028年度以降に化石燃料の輸入事業登録者に対して、輸入する化石燃料に由来する二酸化炭素量に応じて化石燃料賦課金を徴収する考えを示しています。そのため、化石燃料由来のエネルギー使用を続ける企業にとって、調達コストが増加するといった影響は避けられません。二酸化炭素を削減し、再生可能エネルギーへ変換するといった対策が求められています。
環境配慮企業を中心にカーボンニュートラル経営がトレンドとなっている理由
環境配慮企業を中心に、カーボンニュートラルを視野に入れた経営がトレンドとなっています。カーボンニュートラル経営が、企業の競争優位性や成長また企業のブランド力向上に大きく貢献すると考えられており、ここではその理由について解説します。
企業に求められるカーボンニュートラルの取り組み
カーボンニュートラル経営とは、気候変動対策の視点を織り込んだ経営手法です。ビジネスの場面では、RE100やSBTなどのイニシアチブやサプライチェーン全体での削減活動や国境炭素税などの制度適用など、さまざまな場面で、企業のカーボンニュートラルの取り組みが求められています。
これまで、温暖化対策は、国が主導し、企業や国民に義務的な対応を求めることが一般的でした。しかし、2050年の目標を達成するためには、企業が率先して、技術改革、価値観の刷新を進めていかなければなりません。
競争優位性の構築
カーボンニュートラルに関する新規事業を開始したり、商品・サービスの開発・改善を進めたりすることは、企業にとって大きなチャンスと言えます。環境に配慮している企業として、ブランドイメージや知名度が向上します。
競合他社に先駆けて、カーボンニュートラルに取り組む先進的な企業として、カーボンニュートラルに高い関心を寄せる企業や投資家などから選ばれやすくなります。
優秀な人材の確保
企業が気候変動や気温上昇などの環境問題に取り組むことで、社会課題の解決に関心がある社員や求職者を集めやすくなります。カーボンニュートラルを目標とした経済社会システム業務に携わる人員は、2020年から2035年の16年間で、約266万人の雇用が発生するといわれています。カーボンニュートラルの実現に向けたDX人材を確保するためには、気候変動などの社会課題に取り組む姿勢を示し、必要とする人材を効率的に確保していくことが重要です。
世界のリーダー的企業が取り組むカーボンニュートラル
国内はもとより、世界のリーダー的な企業の多くがカーボンニュートラルに取り組んでいます。国内外の企業の取り組み事例を紹介します。
Unilever(ユニリーバ)
英国の日用品・消費財メーカーのユニリーバは、2039年までにサプライチェーンも含めて、原材料の調達から店頭販売・廃棄にいたるすべての過程で二酸化炭素の排出量をゼロにすることを目指しています。
ユニリーバの環境に対する取り組みは、原材料を自然環境に配慮した農園から調達する、再利用可能な容器を利用するなど事業全体に渡り徹底しています。ユニリーバは、2030年までに以下の目標を掲げています。
- 150万ヘクタールの森林・海洋の保護再生を行う
- 気候変動、自然保護、ゴミ削減に1000億円を投資する
- ユニリーバ単独で二酸化炭素排出量ゼロを目指す
2022年の時点で、2015年と比べて二酸化炭素排出量削減率68%、消費電力93%削減を実現しています。
ファナック
産業用ロボットや工作機械用制御装置で、世界でも高いシェアを誇るファナック株式会社もカーボンニュートラルの実現に向けて、中長期の温室効果ガス排出削減に取り組んでいます。目標として、以下を掲げています。
- Scope1、 2 : 2050年までにカーボンニュートラルを達成する
- Scope1、 2 : 2030年までに2020年比で温室効果ガスを42%削減する
- Scope3 : 2030年までに販売した製品の使用による排出量(カテゴリ11)を、2020年比で12.3%削減する
すでに、本社がある山梨県忍野村や栃木県や茨城県の工場では、使用する電力の一部を再生可能エネルギー由来の電力に切り替えています。この取り組みは、国内のさまざまな拠点で随時進めていく予定です。あわせて、太陽光パネルを設置し、事業活動における温室効果ガスの排出量削減を目指しています。
まとめ
企業はカーボンニュートラルの実現に向け、環境配慮を求める投資家や政府の要請に対応する必要があります。ESG投資の拡大や炭素税・排出量取引制度の導入が進み、環境対策は企業経営の重要課題です。また、環境配慮企業は競争力強化やブランド向上のために積極的に取り組んでおり、ユニリーバやファナックなど世界的企業も脱炭素を推進しています。企業は技術革新と価値観の刷新を通じ、持続可能な成長を目指すことが求められています。
現に、国内外を代表するグローバル企業の多くが、カーボンニュートラルにすでに取り組み、具体的な数値目標を掲げています。
カーボンニュートラルへの取り組みが加速するなか、富士通グループは、果たすべき社会的役割を再検討し、2030年度に自社が排出する二酸化炭素を限りなくゼロに近づける目標を掲げています。
- ダウンロードはこちら
ホワイトペーパー:経営層の意識改革の重要性とステークホルダーから求められるアクション
(注)資料のダウンロードにあたり、簡単な登録が必要です。
-
WEBでのお問い合わせはこちら入力フォーム
当社はセキュリティ保護の観点からSSL技術を使用しております。
-
お電話でのお問い合わせ
富士通Japanお客様総合センター
0120-835-554受付時間:平日9時~17時30分(土曜・日曜・祝日・当社指定の休業日を除く)