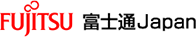カーボンニュートラルとは?企業がいま取り組むべき理由
カーボンニュートラルとは
カーボンニュートラルとは、温室効果ガスの排出量と吸収量を差し引いて「ゼロ」にすることです。日本では、カーボンニュートラルは、二酸化炭素に限らず、メタン、一酸化二窒素、フロンガスなども対象です。カーボンニュートラルの実現には、排出する温室効果ガスの総量を削減することが大前提です。企業がカーボンニュートラルに取り組むことで、地球環境を守るために活動していることを示せます。環境に優しい商品やサービスであることは、消費者や取引先にもポジティブな印象を与えるでしょう。その結果、企業の持続可能な成長にも貢献することにつながります。
なぜ今、カーボンニュートラルが求められるのか?
カーボンニュートラルは、日本のみならず、世界各国で重視されています。カーボンニュートラルが注目される背景には、気温変動問題、気候変動問題が関係しています。2015年に採択されたパリ協定の内容と合わせて、カーボンニュートラルが求められる理由を深堀します。
パリ協定と製造業への影響
パリ協定とは、2015年に採択された地球規模の課題である気候変動問題の解決に向けた世界共通の長期目標です。このなかで、以下をはじめとする気候変動問題を解決するための目標が制定されました。
- 世界的な平均気温上昇を工業化以前に比べて2℃より十分低く保つ
- 平均気温上昇を1.5℃に抑える努力を追求する
- 21世紀後半に、カーボンニュートラルを達成する
パリ協定の目標達成には世界的な取り組みが重要であり、なかでも製造業を筆頭にさまざまな産業での温室効果ガス排出量削減が不可欠です。
気温変動
パリ協定が制定された背景には、世界の平均気温が上昇したことがあります。2024年の世界の平均気温は、工業化以前(1850〜1900年)と比べ、約1.55℃上昇しました。これは、「パリ協定」が目指す上昇幅「1.5℃」を超える値です。
温室効果ガスを排出する状況が続けば、さらなる気温上昇が予測され、製造業のサプライチェーンや事業活動にも大きな影響を及ぼす可能性があります。
気候変動
日本も気候変動による、気温上昇が続いています。2024年の日本の平均気温は、平年値(20年までの30年間平均)を1.48℃上回り、1898年の統計開始以降で最も高くなりました。
長期的には100年あたり1.40℃の割合で上昇しており、とくに1990年以降は、夏日や真夏日を記録する日が増加しています。気候変動をさまざまな自然災害の要因と考える向きもあります。今後、集中豪雨や猛暑のリスクがさらに高まることが予想されます。気候変動は農業や水産業、自然生態系、経済活動などさまざまなジャンルに影響を及ぼしかねません。たとえば、製造業といった関連性がない領域においても、集中豪雨や猛暑といった異常気象の増加に伴い、工場の操業停止やサプライチェーンの混乱といったリスクをもたらします。
世界の潮流と製造業のビジネスチャンス
カーボンニュートラルに向けた動きは、世界で加速傾向です。
COP26
2021年に開催されたCOP26(国連気候変動枠組条約第26回締約国会議)が終了した時点で、154か国・1地域がカーボンニュートラルの実現を表明しました。グローバル市場では、カーボンニュートラルに向けた国際的なルール作りが進み、取引先まで含めたサプライチェーン全体のカーボンニュートラルの実現が求められています。企業はこれらのルールを理解し、迅速な対応を行う必要があります。
ESG投資額
カーボンニュートラルが進み、世界のESG投資額は、2020年に35.3兆ドルまで増加しました。気候変動に関する情報開示を政府だけでなく、企業にも求める動きが広がり、取引先まで含めたサプライチェーン全体のカーボンニュートラルの実現が求められています。デジタル技術を活用し、サプライチェーン上のCO2排出量を算定し、可視化するサービスも活発化しており、製造業にとって新たなビジネスチャンスが生まれています。ESG経営に積極的に取り組むことで、企業価値の向上につなげ、投資家からの資金調達を有利に進めることができます。
カーボンニュートラルへの取り組みを阻害する要因も無視できない
カーボンニュートラルへの取り組みは、決して順調に進んでいるとは言い切れません。
地政学リスクやエネルギー価格変動といった課題が、その進展を阻害しています。国際的な緊張は再生可能エネルギー投資を抑制し、資源の供給不安定化や価格高騰は、企業の脱炭素化への転換を遅らせる要因となります。国際協調の停滞も懸念材料です。各国が自国の利益を優先すれば、国際的な枠組み構築が難航し、カーボンニュートラル達成が遠のきます。自国の天然資源に対する支配権の強化も、再生可能エネルギーに必要な資源供給を不安定化させるリスクをはらんでいます。ロシアのウクライナ侵攻は、その典型例です。また、ドイツはエネルギー危機を受け、石炭火力発電を拡大し、二酸化炭素排出量が増加しました。このような短期的な逆行は起こりうるものの、カーボンニュートラルの重要性は変わりません。最近も、2025年1月にアメリカのトランプ政権からパリ協定から再び離脱する通告がありました。企業はこれらの課題を認識し、長期的な視点で戦略を立てなければなりません。
環境配慮企業が持つ影響力と製造業のリーダーシップと社会的責任
地球温暖化を防ぐ「カーボンニュートラル」の達成には、企業、特に製造業の役割が極めて重要です。世界の温室効果ガス排出量の約24%は産業活動によるもので、その中でも製造業は複雑なサプライチェーン(部品の調達から製品の販売までの一連の流れ)を持つため、排出量削減への責任は重大です。
カーボンニュートラルに向けた経営として、温室効果ガスの排出量削減、再生可能エネルギー利用、省エネルギー推進の3つの取り組みが不可欠です。
まず、製造工程やサプライチェーン全体でどこから多く排出されているかを特定し、効率的な設備投資やプロセス改善が必要です。また、太陽光発電などの再生可能エネルギー導入や、電力購入も有効な手段です。さらに、断熱材導入やLED照明への切り替えなど、省エネ対策も重要です。
これらの取り組みを効果的に進めるためには、パートナー企業との連携が不可欠です。サプライチェーン全体で排出量削減に取り組むことで、より大きな成果を上げることができます。また、政府や自治体の支援制度を活用することも重要です。
環境配慮企業が取り組むことでどのような影響があるか
カーボンニュートラルへの取り組みは、もはや企業の社会的責任になりつつあります。二酸化炭素排出量を総合的に測定し、削減することは、低炭素経済での競争優位につながるだけでなく、以下のような様々なメリットを生み出します。
- 地球温暖化問題への取り組み
温室効果ガスの排出量を削減し、地球温暖化を抑制につながります。 - ステークホルダーからの信頼獲得
環境問題への責任を果たす企業として、顧客や取引先、投資家など、あらゆるステークホルダーからの信頼と信用を獲得できます。 - 企業イメージの向上
環境配慮への意識の高さを示すことで、企業イメージが向上し、ブランド価値を高めることができます。 - 優秀な人材の確保
SDGsに注目する学生が増加しており(就職活動を行う学生の約45%が企業選択のポイントとしてSDGsを重視)、カーボンニュートラルへの取り組みは優秀な人材の確保にも繋がります。 - 先行者利益
他社に先駆けてカーボンニュートラルに取り組むことで、市場での優位性を築き、効果的なプロモーションにもなります。
企業が取り組む際の課題
企業がカーボンニュートラルに取り組む際には、コストがかかることを認識しておかなければなりません。カーボンニュートラルは、経済全体では景気刺激策と同等の効果があるとされています。
カーボンニュートラルへの投資は、長期的にはコスト削減、ブランドイメージ向上、優秀な人材の確保など、様々なメリットをもたらす可能性があるため、戦略的な投資によって、投資対効果を高めることが重要です。
カーボンニュートラルにおける先行取り組み事例
多くの企業が、カーボンニュートラルに向けた取り組みを進めています。なかでも、生産過程で発生する環境負荷として、工場廃棄物や電気・ガス・石油などのエネルギーなどが要因で二酸化炭素排出量の割合が大きい製造業においては、カーボンニュートラルへの方向転換が強く求められています。
カーボンニュートラルを実現するためには、電量のカーボンニュートラル化と生産設備の省電力化が必須です。既存生産設備に老朽化がないか、使用電力量を抑制できないかといった取り組みが、製造業において現実的なカーボンニュートラルへの取り組みです。
製造業において、多くの企業がカーボンニュートラルの実現に向けて活動を進めています。
ここでは、カーボンニュートラルに取り組む製造業の事例として、日本製鉄、トヨタ自動車株式会社を紹介します。
日本製鉄
鉄鋼メーカーとして、世界でもトップクラスの規模を誇る日本製鉄株式会社は、2030年までに2013年度対比で30%の二酸化炭素削減のシナリオを掲げています。積極的な技術開発を行い、カーボンニュートラルを目指しています。
- 大型転炉での高級鋼の量産製造
- 水素還元製鉄やCCUSの開発
トヨタ自動車株式会社
トヨタ自動車株式会社では、「工場CO2ゼロチャレンジ」を制定して、2030年までに2013年と比較して工場の二酸化炭素排出量を35%以下にすること、 2050年には実質ゼロにすることを掲げています。具体的な取り組み策は、以下のとおりです。
- シンプル・スリム・コンパクト化...製造見直し、工程短縮・集約
- エネルギー効率改善...捨てていたエネルギーの回収
- ムダ、ムラ、ムリの徹底排除
まとめ
環境配慮企業には社会的責任があるという概念が浸透しつつある現在、カーボンニュートラルに環境配慮企業が取り組むことが欠かせません。とくに製造業においては、二酸化炭素排出量の割合が大きく、カーボンニュートラルに向けた取り組みは急務です。カーボンニュートラルの実現に向けて、電量のカーボンニュートラル化と生産設備の省電力化を進めましょう。
- ダウンロードはこちら
ホワイトペーパー:企業の持続可能な成長を促すカーボンニュートラルへの包括的な取り組み
(注)資料のダウンロードにあたり、簡単な登録が必要です。
-
WEBでのお問い合わせはこちら入力フォーム
当社はセキュリティ保護の観点からSSL技術を使用しております。
-
お電話でのお問い合わせ
富士通Japanお客様総合センター
0120-835-554受付時間:平日9時~17時30分(土曜・日曜・祝日・当社指定の休業日を除く)